 航空機
航空機 次世代航空機の開発動向(Ⅰ)
次世代航空機の開発動向は、同様に低環境負荷を目指す次世代自動車と良く似ている。ただし、次世代航空機ではバイオジェット燃料の供給の可能性は十分にあるとして、空港のインフラ整備による持続可能な航空燃料(SAF)の検討が進められている。一方で、ハイブリッド機→電動航空機・燃料電池航空機・水素タービン航空機へと向かう研究開発が始められている。
 航空機
航空機  いろいろ探訪記
いろいろ探訪記  エネルギー
エネルギー 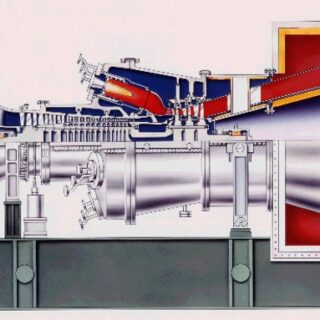 エネルギー
エネルギー  いろいろ探訪記
いろいろ探訪記 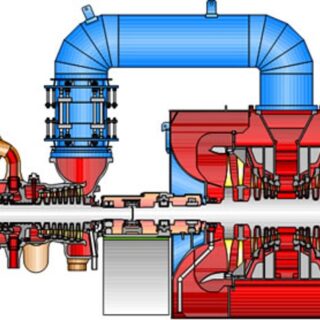 エネルギー
エネルギー 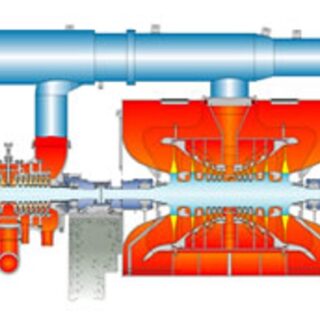 エネルギー
エネルギー  エネルギー
エネルギー  自動車
自動車  自動車
自動車